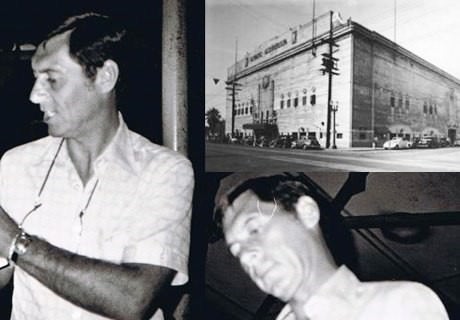異種格闘技戦とは何か? 天使と野心家~アリ猪木40年目の解析
niconico動画の『巌流島チャンネル』でほぼ毎日更新していた「ブロマガ」が、オフィシャルサイトでパワーアップして帰ってきました。これまでの連載陣=谷川貞治、山田英司、ターザン山本、田中正志、山口日昇に加え、安西伸一、クマクマンボ、柴田和則、菊野克紀、平直行、大成敦、そして本当にたまに岩倉豪と、多種多様な方々に声をかけていく予定です。ぜひ、ご期待ください!
6月20日(月)のブロマガ………お題「40年前の猪木 vs アリ戦を見て、異種格闘技戦を考える!」
The Greatest”モハメド・アリが、蝶となり飛び立った。74歳だった。プロレス界とはフレッド・ブラッシーにTalkerのルーツがある実像のアリは、ケンタッキー州ルイビル出身。アフリカ系アメリカ人で徴兵拒否と「蝶のように舞い、蜂のように刺す」のタタキ文句で知られ、黒人差別とも闘ってきた戦士であることが、伝説を不滅にしている。
1974年10月30日、ジョージ・フォアマンと中部アフリカのザイール(現コンゴ)で対戦。8Rでの一発大逆転を演じた『キンシャサの奇跡』にて、ライセンスはく奪期間含む3年7ヶ月間のブランクを経て、7年ぶりに世界ヘビー級王者に返り咲く。
翌年3月24日、無名のチャック・ウェプナーと初防衛戦を行うが、格下の当て馬に善戦され15R開始のゴングが鳴ってもウェプナーはリングに立っていた。これを見たシルヴェスター・スタローンが映画『ロッキー』の脚本を書きあげ、運命の歯車が回り始める。
ジョー・フレージャーとの“The Thrilla in Manila”を制し、黒人最強、白人最強を倒して「次は東洋人か」というリップサービスに過ぎなかったいつもの煽りに、「資金の工面はあとから考える」フライング昭和プロレス=アントニオ猪木&新間寿営業本部長の新日本プロレスが噛みつく。600万ドル(約20億円弱)をふっかけられたが、ドン・キホーテは見果てぬ夢を追ったのだ。
一方、ヨーコ・オノが付いて装填されたジョン・レノンのように、倍賞美津子との共闘戦士と化したアントニオ猪木は、いよいよ狂い咲く1976年を迎える。今から40年前、マット界は転換点を迎えていた。異種格闘技戦とはなんであったのか?
▼アリが本当の神だった!プロレス芸術とは? 徹底検証:テレビが伝えなかったアリ猪木戦の裏
http://miruhon.net/item/index.php?main_page=product_info&cPath=2_8&products_id=348
アリ猪木には数々の階層に踏み絵がある。ファンのメディア・リテラシーが試されることもそのひとつであり、すべての”権威”は疑ってかかる必要がある。1976年3月25日、ニューヨーク・プラザホテルでの調印式、BENIHANAステーキで地元名士に上り詰めたロッキー青木がMC務める顔見世回、アリは「ボクシングで一番小さいグローブは6オンスだが、さらに小さい4オンスで闘ってやる」と述べている。
あまりの大凡戦に、米国側の当時の記者記事などが埋もれてしまったが、「アリの次戦が日本でプロレスラーとエキシビション」は、最初からアリ本人より約束され、現地のメディアもそう報道した。ところが集英社版DVDというか当時のテレ朝、「せいぜい一番小さなクラスのボクサー6人で十分だが、それに4人の女性を加えてやる」との、史上空前の珍訳テロップで誤魔化された史実をご存じだろうか?
アリ猪木とは、マット界史上最大の誤解が曲解を呼び、プロレスをよくわかってない通訳さんなり、(意図的可能性も捨てきれない)誤訳テロップが絡むという伏魔殿の構造が無数の関係者含む語り部を生んだ特異な伝説イベント例である。後出しじゃんけんの評論家解説や文化人プロレスファンが加わるたびに、さらに珍騒動が多重に歪曲化されていった、日本人ファン気質を海外目線から研究する際のケース・スタディーに違いない。
日本武道館、6月26日。アリはテーブルに3つのグローブを置いてボクシング記者にも合図している。8オンスならガチ、4オンスの練習用ならエキシビション、サンドバック用を選べば危険シグナルで、最初からプロモーターに大恥をかかせるコメディ戦アピールだ。本気で殴らないことをカセットテープ録音で誓約までした天使のアリは、だらっと広げれば大きくなる4オンスを選んでゲートに向かった。
アリ猪木の真実は、「本当のがんじがらめ制約」を受けても国際親善試合を成立させたアリこそが神だったと察することに他ならない。
アリは必死でお客さんと戦っていた。しょっぱい仕事しか成立しえない試合をやる嵌めになった寝転がった猪木を見ながら、ビッグマウスの声でお客さんになんとか訴える試合を作ろうとしていた。それを大きく拾うリミックス作業は称賛しておきたい。しかし、例えば「プロレスにキックはねえだろ」とイチャモンつけてるだけのことで、まず翻訳がニュアンスわかってない。
また、マーク役だったカール・ゴッチ先生の英語の指示テロップ再現でも、猪木本人がまったく聞いていないもの入れて画面が賑やかにはなるが、真実から遠ざかってしまった今回の追悼番組の目玉「音で新事実」の歪曲の笑撃は凄まじい。
白のバンテージが軸足の左にというお仕事遂行中の両雄再確認は、テロップ等にはスルーされていたからだ。終盤に回数集中させるCM空け、両雄の流しが始まった14R、「ゲスト:石坂浩二」の音声が出る。笑撃だ。なるほど、その手があったか。お茶の間はますますわからなくなる番組構成ではあった。
お互いが裏切られる恐怖から踏み込んだ攻防のないまま3分15R引き分け。手数がどうの以下、もっともらしい解釈を後付けする評論家が未だあとをたたないが、「本気で殴らない」と確約している以上、決まっているケツに向かう採点表で、ポイントがどうのはいかに滑稽な議論かおわかりだろう。ジャッジ判定は、三者三様の「猪木」「アリ」「引き分け」1-1発表である。両雄のメンツを守る口約束は忠実に履行された。
互いが絶対的な信頼のもとで頭や体を相手に委ねる“仕事”のマッチメイクではなかったとはいえ、ケツが決まっている試合を「これぞ真剣勝負! だからつまらない試合になった」と美談にするには無理があり過ぎる。世紀の一戦に当初から疑問の目を向けるボクシング記者の追求もあり、肝心の打ち合わせとリハーサルなどできるわけもなかった追い詰められた状況が膠着試合を生んだ。つまり、報道マスコミがプロレス記者だけではなかったことで、謎の試合として神秘性を高めた皮肉がある。
のちの対マーシャルアーツ王者とか、そういう選手なら事前の煽り段階の会見や公開練習で余計なツッコミをする記者は皆無だが、ボクシング世界王者となってくると格と知名度が違うため、そうは問屋が卸さない。カネさえ払えば何でも出来ると安易だった主催の新日本プロレスとテレビ朝日は面食らった。“ショー”であることを察知されることなく、いかにして“ショー”を遂行するか―――そういう意味では、両者は「決着つかずのドロー15R」という、体力なければそもそも厳しいシナリオ遂行のために真剣に戦うという、実に奇妙かつ、壮絶なプレッシャーが両雄に課された超緊迫の大一番だった。
誤解してほしくはない。さまざまな観点からもこの対決の歴史的意義は不滅である。未知との遭遇にお互いが恐怖とも闘っていた。「一発当たればKO負けになる」。他競技のプロ世界王者となってくると破壊力が尋常ではない。記憶が飛ぶ恐怖は試合前の悪夢にも出てきたそうだ。
本番でも金縛りのままで恥ずかしい限りだったというのが、当時33歳アントニオ猪木の素の本音である。「グランドでの攻防はナシ、関節技で極めることもない」は対ボクサー戦で自然のこと。一方、提携するロス地区プロモーター=マイク・ラーベルの弟ジーンは、専門誌向けにはアリ側との触れ込みだがプロレスのレフェリーだ。ボクシングにはない、能動的にロープブレイクに持っていく役割がある。しかし、倒されたら「スニーキー(ずる賢い)イノキに何をされるか分からない」リスクは残るのだ。離れ際に反射神経でヒジをコメカミに落とされたらどうするのか。アクシデントも起こりうる「闘い」にカテゴリー分けの貴賤はない。
結局、アリは本気で殴らないが、組み付いて締めたり、逆関節はナシ。突っ込んで来ないでくれ、飛び込んだらそこで仕切り直しとなると、仮にもしブッカ―(現場監督)の課題を与えられても試合の作りようがない。もっとも、このカードをプロレス側からばかり論じてしまうガラパゴス国の問題点になるが、米国でもクローズド・サーキット衛星中継される「アリの次の闘いは日本から」という大前提を忘れては、全体像の冷静な分析にならない。UWFもUFCもなんもない、キックボクシングの理解すらないこの時点での北米ファイト好きファンにも、カネ取って見せる「ボクサー対レスラー」である。
一方がグローブを付けてないだけでも異様なことなのだが、基本はボクシングに則る了解は仕方のないこと。ガチなのか否かの二元論は時代背景からも曲解の元になりかねず、猪木が踏み込んで柔道技で投げることも、関節を取ることも北米の客にはそもそも反則にしか見えない。当時の現実を無視しての議論は本末転倒だ。
アリ側が一方的にルールを押し付けた訳ではない。そもそもワークのプロレスと、競技のボクシングの代表同志が闘うったって、ヤオガチ以前にそもそも何が公平で中立なのかと、インテリ識者なら落としどころが見えない。打撃も寝技も関節技も必修の、のちの総合格闘技MMAがない1976年だ。すべてをクロストレーニングする発想すらなかった世界地図において、海外配信を踏まえた常識があったに過ぎないのである。
寝転がったまま相手の足裏を蹴り上げることを除いて、他に何をどうすればよいのか。逆から考えると見えてくるものだ。事前のデモンストレーションとして、ゴリラ・モンスーンとのTVマッチ収録なら、相手が2分で倒れてくれるから派手にエアプレンスピンを受けて問題ない。しかし、猪木が反則で勝つがアリも「パールハーバー奇襲の不意打ちだった」と、面子を守るA案ではなく、「どうせ八百長やるんだろう」とボクシング記者からのガチ質問に、きっぱりと真剣勝負を口にした手前、のちのモンスターマン戦のような、前日リハーサルで派手に魅せる試合を作るB案も使えない。「引き分け」しか両英雄の名誉を守る結末はなかった。
テレビ朝日のアリ追悼番組:蘇る伝説の死闘「猪木VSアリ」は、6月12日(日)夜8時58分から2時間強のゴールデン枠を貰い、8・5%の高平均視聴率を記録した。テロップやカット割り、面白かった部分だけ強調再生の再編集で、あらたに音声も拾ったというのが40周年リミックス版の売りだが、お客さんに聞こえる前提のトラッシュトークの解析より、表情の分析の方が映像を読み解く近道なのは自明のこと。
セコンド陣が動き出す4R、下からの猪木の蹴りに、アリがコーナーを背にトップロープで足を宙に浮かせながら挑発する場面が2度、のちに写真で使われることも多いスポット絵となる。そのあとの5R、回し蹴りにグラッときたアリがロープ持って立ち上がった際、猪木がすかさず掴みに行く素振りを見せるも、実況通りの千載一遇のチャンスに猪木は追わない。その瞬間のジーン・ラベルの表情に注目して欲しい。「ほっとすると同時に、これでイイんだ」と自身に二度頷いている。
怖かったから、さらに一歩踏み込めなかった本音もあるが、突っ込んでもそこでレフェリーが入るだけだった仕切りの核心は、これまで様々な権威ある媒体がアリ猪木解明を取り上げてきたが、どこにもない切り口で活字にしているのは記者だけだろう。以降、似た場面になるとレフェリーの割って入り方から暗黙の間合いが合意形成されているのが読める。より詳細な資料付き長編ルポタージュ考察は、どうか電子書籍購入をお願いするばかりだ。
新間寿営業本部長はひたすら金策に奔走してしまい、リング上でどうするかを社長任せにした大罪を反省したが、大半の客が途中で帰ったとも伝えられる米国配給パートナーからナイフを贈られ、切腹を迫られた逸話が残る。どんなに「総合格闘技の原点」とのちの再評価で祭り上げられようが、リングサイド最前列席30万円のプレミアム・イベントがお客様に不満を残し、大凡戦と断罪され、世間から笑われた事実は悔やまれる。
猪木と仲たがいした時期に「がんじがらめルール」が業界アングルだったことをアサヒ芸能の連載でぶちまけてしまっている通り、膨大なルール契約書などは錯覚だ。アリが肉声をカセットに残して「裏切ったりはいたしません。全力で殴りません」を誓約しただけである。しかし、猪木のヒジが咄嗟に入ってしまうのと同じで、軽いジャブのつもりが急所に当たってしまうことはありうるのだ。それが4発とも5発ともカウントされたアリのパンチ数である。
絵として闘いがどうなる壮大な実験なのか、両雄戦士も、取り巻き陣営も、誰も何もわからなかった。この出発点を反芻しない限り、のちになって「猪木アリ状態」と実況アナが表現する、MMAリアルファイトの現場で実際に繰り広げられる光景の誕生はない。安易なヤオガチ論は底なし沼に突き落とされた。
40周年番組が放送されてもなお、大半の昭和プロレスファンにとって「世紀の対決」深層理解に進歩はないのかも知れない。十人十色の趣味の世界なんだから、好きに解釈を楽しませてくれという選択肢は尊重しておきたい。また、記録より記憶がプロレスのすべてだとするなら、「猪木はがんじがらめのルールで、アリとの不利な闘いに挑んだ」と死ぬまで思い続けるのだから、「錯覚のビジネスに真実は求められてない」論は昔から諭されてきた命題でもある。
多数派プロレスファンの趣向に合わせる週刊プロレスとは、照準が違うのだから比較に意味はない。格闘技専門誌から別冊宝島や東スポまで、同じにする意味も必要もない。唯一、卒業しない楽しみ方に少しでも興味持っていただけるなら、大人のファン向きに特化したマット界情報誌・週刊ファイトを試して欲しいだけ。楽しみ方の改宗まで求めてないが、食わず嫌いや偏見は捨てるべきとの信念はある。
すべてが無謀スケールの、しょせんはイケイケ個人商店のプロレス団体が向こう見ずな興行をした茶番劇だったと、世間側の媒体が報道した酷評がまっとうだった点は、いかに頑固な猪木信者といえども認めるべきだ。そこをなかったことにして美談へのすり替えは歴史の歪曲になる。
力道山が未知のプロレスリングを日本に紹介した際、大手新聞所属記者といえども仕組みをわかって書いている者と、ガチと疑わずにスポーツ評する記者に分かれ、毎日新聞と朝日新聞が喧嘩になって「ショーだ」と活字に出てしまったことがあった。律儀にもあっという間に観客が落ち込んだそうだが、エンタメ路線を開き直った力道山は、怪奇派マスクマンなどを集結させた『ワールドリーグ』を開催して盛り返した。権威あるプロレス専門誌の歴史読本には核心がスルーされている観客激減の発端話のことだ。
世界中から笑われ巨額の負債を抱えたアリ戦のマイナスから、1972年設立の新日本プロレスは眠れる獅子が覚醒する。キンシャサの奇跡で叫ばれた現地語「ボンバイエ!(殺せ)」を応援歌にしたアリのワクワクさせる入場曲使用が許諾され、アントニオ猪木は秘めたるリベンジを胸に、教訓をバネに異種格闘技戦をシリーズ化していく。絶望さえも光になる。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■週刊ファイト6月16日号アリ神/新日W-1全日x元子/BレスナーUFC/ダンヘン最後/キンボスライス死/ミャンマーラウェイ
http://miruhon.net/item/index.php?main_page=product_info&cPath=2_8&products_id=877